-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
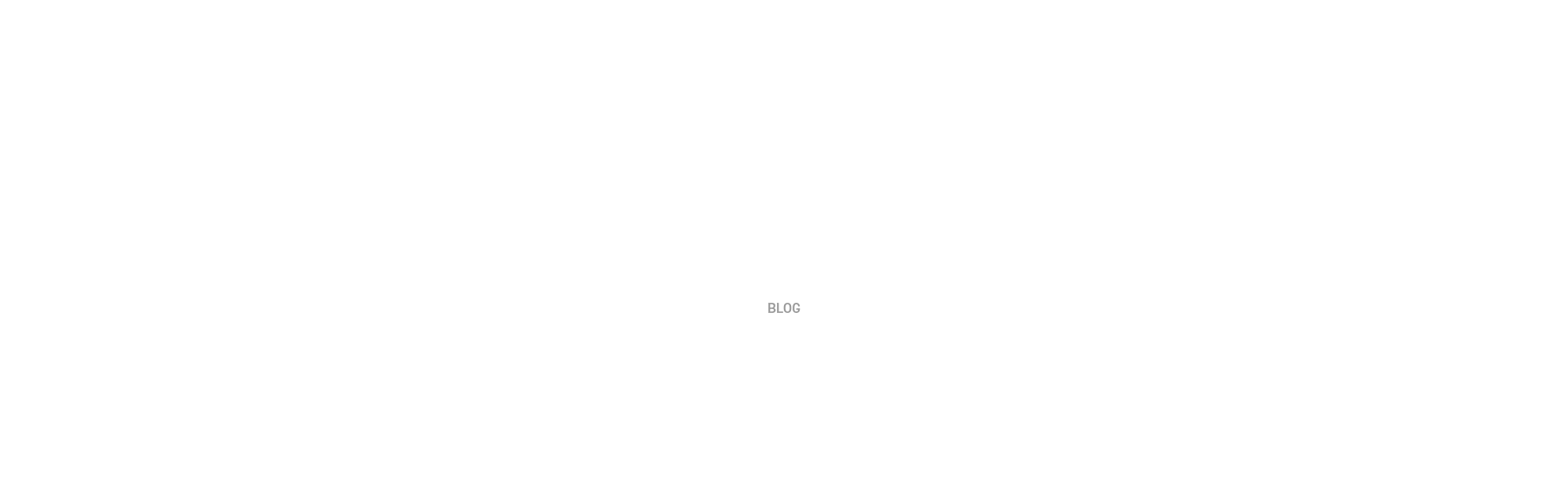
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
家具建具工事は、ただ取り付けるだけの工事ではありません。
一つひとつの工程を丁寧に積み重ねることで、
長く快適に使える家具・建具が完成します。
すべての始まりは、
現場での正確な採寸です。
壁の歪み
床や天井の不陸
既存建具との取り合い
図面だけでは分からない情報を、
実際の現場で確認します。
採寸データをもとに、
寸法
金物位置
納まり
を考え、
設計・図面を作成します。
この段階での判断が、
仕上がりの良し悪しを左右します。
図面に基づき、
工場で家具・建具を製作します。
材料選定
加工精度
金物下穴加工
どれも妥協できない工程です。
完成した家具・建具を
現場へ搬入します。
養生
搬入経路の確認
破損防止
細心の注意を払いながら作業します。
現場での取り付けは、
職人の腕の見せどころです。
水平・垂直調整
金物の取付
扉のクリアランス調整
少しのズレも見逃しません。
取り付け後は、
開閉確認
音のチェック
鍵・クローザー動作確認
を行い、
最終調整を行います。
最後に、
図面通りか
不具合がないか
お客様が使いやすいか
を確認し、
工事完了となります✨
家具建具工事は、
覚えることが多い
最初は難しく感じる
仕事です。
ですが、
採寸ができるようになる
図面が読めるようになる
調整でピタッと決まる
この瞬間に、
大きなやりがいを感じられます。
「形に残る仕事がしたい」
そんな方に向いている仕事です。
家具建具工事は、
正確な採寸
丁寧な製作
確実な取付と調整
この積み重ねで完成します。
見た目だけでなく、
長く使えることが何より大切です。
本年も多くの家具建具工事に携わらせていただき、誠にありがとうございました。
一つひとつの現場で、丁寧な仕事を積み重ねてこられたことに感謝しております。
来年も、
使う人の立場に立った家具・建具づくりを大切にし、
安心して任せていただける工事を行ってまいります。
どうぞ良いお年をお迎えください
次回もお楽しみに!
塩見木工所株式会社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
塩見木工所株式会社では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
建具や家具というと、
どうしても「扉のデザイン」「木目」「サイズ感」といった
見た目の部分に目が行きがちです。
しかし、実際の使い心地や寿命を左右しているのは、
**建具金物(かなぐ)**と呼ばれる存在です🔧
建具金物とは、扉や引き戸、家具に取り付けられる
機能を支える部材の総称です。
代表的なものには、
🔹 蝶番(ちょうばん)
🔹 レール
🔹 ドアクローザー
🔹 鍵
🔹 取っ手・ハンドル
などがあります。
一つひとつは小さな部材ですが、
毎日の開け閉め・安全性・耐久性を大きく左右します。
蝶番やレールは、
建具の「動き」を決める重要な金物です。
開けたときの重さ
スムーズさ
音の静かさ
これらはすべて、
蝶番やレールの性能・取付精度によって決まります。
安価な金物を使うと、
ガタつきが出る
扉が下がる
異音が出る
といった不具合が起こりやすくなります⚠️
鍵やドアクローザーは、
安全性と快適性を支える金物です。
鍵
→ 防犯性・プライバシー確保
ドアクローザー
→ 扉の閉まり方をコントロール
特にドアクローザーは、
バタンと閉まらない
指はさみ防止
建具への衝撃軽減
といった役割を持ち、
建具の寿命にも大きく関わります。
取っ手やハンドルは、
毎日必ず手に触れる部分です。
握りやすさ
手触り
高さや位置
が少し違うだけで、
使いやすさが大きく変わります。
デザイン性だけでなく、
実際の使い勝手を考えた選定が重要です✨
建具金物の取付は、
ミリ単位の調整
建具のクセを読む力
経験に基づく判断
が求められる作業です。
同じ金物を使っても、
取付ける人によって
動き
音
耐久性
が変わります。
小さな部材ほど、技術の差が出る。
それが建具金物の世界です。
建具金物は、
🔧 小さくても重要
🚪 使い勝手を大きく左右
🏠 建具の寿命を延ばす存在
です。
「ちゃんとした建具」は、
見えない部分がしっかりしています。
次回もお楽しみに!
塩見木工所株式会社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
塩見木工所株式会社では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
🏗️金属建具の特徴 ― 強さと機能性で進化を続ける現代の建築素材
〜アルミ・スチールが支える快適な暮らし〜
現代建築において、金属建具は欠かせない存在です。
ビルのサッシ、店舗のドア、住宅の窓枠――
どこを見ても、アルミやスチールの建具が日常に溶け込んでいます。
強さ・耐久性・気密性・防火性。
これらを高次元で兼ね備えたのが、金属建具の魅力です。
アルミやスチールは、腐食に強く変形しにくい素材です。
湿気や紫外線、風雨にさらされても劣化が少なく、長期間にわたって美観を保ちます。
特にアルミサッシは軽量で錆びにくく、住宅の窓やドアに最適。
スチール建具は強度に優れ、公共施設や工場など耐久性を重視する建物に多く採用されています。
さらに、塗装やメッキ処理によってメンテナンス性も向上。
外壁との調和を図るデザインカラーも増え、見た目と性能の両立が進んでいます。
金属建具は、密閉性の高い構造により、冷暖房効率を高める役割を果たします。
最新のサッシでは、アルミと樹脂を組み合わせた複合構造が主流になり、
外気の影響を最小限に抑えつつ、結露の発生を防ぎます。
遮音性にも優れているため、
都市部の住宅やオフィスでは「静かな空間づくり」にも貢献。
防音ガラスや二重サッシとの組み合わせで、快適性が格段に向上します。
スチール建具や防火戸は、高温にも耐える耐火性を備えています。
火災発生時に延焼を防ぎ、避難経路を確保する重要な役割を担います。
また、近年では防犯対策として、
強化ガラスやマルチロック構造のドアが増え、
安全性と安心感を高める建具が主流になっています。
金属建具=無機質、という時代はもう過去のもの。
今では、木目調塗装・カラーアルマイト・ヘアライン加工など、
素材の美しさを引き出すデザイン技術が進化しています。
スタイリッシュな外観、シャープなライン、光を取り込む透明感――
現代建築における「金属建具」は、単なる機能部材ではなく、デザイン要素としての存在感を放っています。
金属建具は、製作段階からミリ単位の精度が求められます。
建物の構造に合わせて寸法を調整し、気密パッキンやシーリングで仕上げる。
そのすべての工程が、建物の性能と耐久性に直結しています。
工場製作と現場施工が密に連携することで、
美しさと強さを兼ね備えた仕上がりが実現します。
木製建具が「温もりとやさしさ」を表現するなら、
金属建具は「強さと機能美」を象徴する存在です。
どちらも建物の個性を形づくる大切な要素。
木のぬくもりと金属のシャープさ――
異なる素材が共存する現代の建築空間は、
まさに技術とデザインの融合によって成り立っています。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
木製建具の魅力 ― 自然素材が生み出す“温もりと品格”
〜手仕事のぬくもりが息づく空間づくり〜
建築の世界で「建具(たてぐ)」といえば、ドア・窓・ふすま・障子など、
人と空間をつなぐ“境界”の役割を果たす重要なパーツです。
その中でも、木製建具は昔から日本の住まいに欠かせない存在。
木の質感・香り・表情は、他の素材では決して真似できない独特の魅力があります。
木製建具の最大の特徴は、自然が生み出す優しい風合いです。
木目の一筋一筋には個性があり、同じ木でも色味や節の出方が異なります。
年月を重ねるごとに艶が増し、経年変化による“味わい”が出てくるのも魅力。
それは、まるで人が歳を重ねて深みを増すようなもの。
和室の障子や欄間、框(かまち)戸など、
光を柔らかく透かす木の建具は、どこか懐かしく、心を落ち着かせてくれます。
木は「呼吸する素材」といわれます。
湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥すると放出する――。
この調湿効果によって、室内の空気を自然に整えてくれます。
特に日本のように四季があり、湿度変化が激しい気候では、
木製建具は室内環境を快適に保つ“天然の調湿器”のような存在です。
夏の蒸し暑さをやわらげ、冬の乾燥を和らげる。
木の力が、暮らしの中に自然な安らぎをもたらします。
木は切る・削る・彫るなどの加工がしやすく、
職人の手によって多彩なデザインを生み出すことができます。
格子戸・組子細工・欄間彫刻など、
日本の建具職人たちは古くから木の特性を活かし、
“機能美と芸術性”を融合させた空間づくりを実現してきました。
現代の住宅でも、無垢材や集成材を使った建具は人気が高く、
ナチュラルインテリアや高級住宅、旅館、茶室など、
“静けさと温もり”を演出したい空間に選ばれています。
木製建具は、金属や樹脂製と違って手をかけるほどに美しくなる素材。
乾拭きやオイル塗布を定期的に行えば、
ツヤが増し、木目がより際立ちます。
小さな傷も「味」として受け止められるのが木の良さ。
家族の歴史とともに成長していく建具は、まさに“住まいの記憶”です。
木製建具は、自然素材のぬくもり・調湿機能・美しい造形――
すべてが調和した「人と暮らしに寄り添う素材」です。
最新の住宅トレンドの中でも、
“木のある空間”は再び注目を集めています。
木製建具があるだけで、
家が「住まい」から「癒しの場所」へと変わる――
そんな力を持つ、時代を超えた建築素材なのです。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
〜素材で変わるデザイン・質感・機能〜
建具の魅力を決めるのは、形だけではありません。
素材の選び方によって、デザイン性・耐久性・コスト・手触り・重量感がすべて変わります。
ここでは、建具に使われる代表的な素材を一つずつ深掘りして紹介します
古来より愛され続ける自然素材。
木目の美しさと温もりが最大の魅力です。
ヒノキ・スギ・ナラ・ウォールナットなど、樹種ごとに香り・色味・硬さが異なり、
使用する部位によっても印象が変わります。
また、木は呼吸する素材。湿度を調整し、心地よい空気環境を保ちます
ただし、乾燥や湿気による反り・割れには注意が必要です。
薄くスライスした木材を層状に貼り合わせた素材。
無垢材の風合いを保ちながら、反りにくく強度が均一なのが特長です。
コストパフォーマンスに優れ、住宅や店舗、公共施設など幅広い建具に使用されます。
最近では、**突板仕上げ(天然木を薄く貼る加工)**によって高級感を出した製品も多くなっています。
木材を繊維状にして圧縮・成形した人工素材。
表面が非常に滑らかで、塗装や化粧シートとの相性が抜群
反りや割れが少なく、加工の自由度が高いため、
室内ドアや造作家具の扉など、デザイン性重視の空間に適しています。
耐久性・防火性・防犯性に優れた金属素材。
学校・病院・工場・オフィスビルなどの公共建築で多く採用されています。
冷たい印象になりがちですが、マット塗装や木目転写などの仕上げ技術により、
近年ではデザイン性も大幅に向上✨
“無機質でスタイリッシュ”な空間演出にもピッタリです。
軽量で錆びにくく、耐久性・施工性ともに優秀。
サッシや玄関ドア、パーティションなどに広く使われています。
アルマイト処理や粉体塗装などにより、
表面仕上げの自由度も高く、メンテナンスが簡単。
現代建築の「軽やかでシャープなデザイン」を支える代表素材です。
光を通しながら空間を仕切る、もっとも透明感のある素材。
透明ガラス・フロストガラス・ミラーガラスなど多様な種類があり、
採光性とプライバシー性を両立できます
さらに、強化ガラス・合わせガラス・Low-Eガラスなど、
安全性・断熱性・防音性を高めた製品も数多く存在。
インテリア建具だけでなく、店舗のショーウィンドウなどにも利用されています。
建具の素材選びは、デザイン・耐久性・コストのバランスを取る重要なポイントです。
木材の温かみ、スチールの堅牢さ、ガラスの透明感──。
それぞれの素材が空間に異なる「個性」と「質感」をもたらします✨
理想の建具は、見た目の美しさだけでなく、
使う人の暮らし方や建物の目的に合わせて選ぶことが大切です。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
〜空間の印象を決める“開け方”とデザインの関係〜
建具(たてぐ)は、単なる「扉」ではありません。
空間を仕切り、光や風、音、視線をコントロールすることで、住まいの快適さや印象を大きく左右する重要な要素です
日本の住宅や建築空間では、昔から気候・文化・暮らし方に合わせて多様な建具が発達してきました。
ここでは、代表的な建具の種類を一つひとつ詳しく見ていきましょう
横方向にスライドして開閉する建具。
限られたスペースでも開閉でき、狭小住宅や通路にも最適です。
近年は、デザインや機能が大きく進化しています。
例えば、ソフトクローズ機構を搭載し、静かに閉まるタイプや、
上吊り式レール構造で床に段差が生じないバリアフリー仕様も登場✨
また、ガラス入りや木目調などデザインも豊富で、
住まいのスタイルに合わせた空間演出が可能です。
➡ メリット: 開閉時に場所を取らず、デザイン自由度が高い
➡ デメリット: 密閉性や遮音性は開き戸に劣る場合がある
もっともポピュラーな建具で、ヒンジ(蝶番)を軸にして開閉します。
プライバシー性が高く、遮音・断熱性能にも優れるため、寝室や個室に多く使われます。
デザインの自由度も高く、ガラス入りの採光ドアや、クラシカルな框組(かまちぐみ)など、空間に合わせた表現が可能。
また、ドアクローザーやスマートロックを組み合わせれば、より快適で安全な住環境が実現します。
➡ メリット: 密閉性が高く、防音・断熱に優れる
➡ デメリット: 開閉にスペースが必要
扉を折りたたむようにして開閉するタイプ。
クローゼットや間仕切りなど、可動範囲を抑えたい場所に最適です。
折り戸は、引き戸と開き戸の“中間的存在”とも言える建具で、
開放感を保ちながらも、全開時にすっきりと収まる構造が魅力
最近では、軽量化と静音設計が進み、
マンションの収納や店舗のバックヤードなどでも多く採用されています。
日本の伝統的建具といえばこれ。
木枠に和紙を貼り、柔らかく光を通す障子は、古くから“日本の美”を象徴してきました。
現代では、破れにくい合成紙やUVカットフィルムなどを用いた機能性障子も登場。
リフォーム住宅やホテルの和モダン空間でも人気です。
➡ 魅力: 光を拡散させ、やさしい空間を演出
➡ 注意点: 紙部分が湿気や衝撃に弱い
和室の間仕切りとして使われ、表面には紙や布が貼られた建具。
模様や質感で空間を彩ることができ、デザイン性が非常に高いのが特徴です。
襖紙を季節やテーマに合わせて張り替えることで、
部屋の雰囲気を簡単に変えることもできます。
➡ メリット: デザイン性が高く、張替えも容易
➡ デメリット: 湿度変化で反りが出やすい場合がある
細い木の桟を組み合わせた格子状の建具。
通風性を保ちつつ、外からの視線をほどよく遮ります。
町家や旅館などでよく見られるほか、最近では**店舗のファサード(正面デザイン)**にも多く使われています。
光と影のコントラストが美しく、見る角度で表情が変わるのも魅力です✨
現代建築に欠かせないのがサッシ。
アルミや樹脂枠にガラスを組み込み、気密性・断熱性・防音性を実現します。
住宅用では「引き違い窓」「縦すべり出し窓」など、形状も多様。
樹脂サッシや複層ガラスを採用することで、省エネ性能の向上にも貢献しています
建具は単なる“仕切り”ではなく、空間を演出する重要なデザイン要素です。
引き戸で広がりを、開き戸で静寂を、障子で柔らかさを、
建物の用途やライフスタイルに合わせて選ぶことが、快適な空間づくりの鍵です✨
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
日常生活の中で「物が片付かない」「収納が足りない」といった悩みを抱える人は少なくありません。
その解決策となるのが 収納家具工事 です。
既製品の棚やタンスを置くだけではなく、空間に合わせて収納を設置・固定することで、暮らしやすさと美しさを同時に実現します。
クローゼット
洋服を効率よく収納。ハンガーパイプ・棚板・引き出しを組み合わせ、衣類だけでなく小物も整理できる。
下駄箱(シューズボックス)
玄関の第一印象を決める家具。扉付きで見た目をスッキリさせ、通気性の良い設計で湿気やニオイ対策も可能。
キッチン収納
食器や調理器具を整理。作業動線を考慮した配置で「取り出しやすさ」が家事効率を大きく左右します。
TVボード・リビング収納
配線を隠しつつ、生活感を抑えたリビング空間を演出。オープン収納と隠す収納のバランスも大切です。
現場調査
間取り・寸法・壁や床の状態を確認。
打ち合わせ・設計
収納量・高さ・生活動線を考慮し、最適なプランを作成。
製作・加工
オーダーメイドの場合は工場で加工し、現場に搬入。
設置・固定
家具を壁や床にしっかりと固定し、転倒防止や安全性を確保。
仕上げ・調整
扉や引き出しの動作確認、水平器で傾きチェックを実施。
空間を最大限活用
梁や柱のあるスペース、狭い空間でも無駄なく収納を確保。
高い安全性
家具を固定することで、地震や衝突による転倒を防止。
デザインと統一感
壁や床と一体化した収納は、空間全体を美しく見せる。
生活効率アップ
物が整理整頓され、取り出しやすくなることで、日常のストレスが軽減。
「見せる収納」+「隠す収納」の組み合わせ
省スペースで大容量を叶えるスライド収納
抗菌・防臭加工の棚材を採用した衛生的な下駄箱
IoT対応で照明やコンセントを組み込むスマート収納
暮らしの多様化に合わせ、収納家具も進化を続けています。
収納家具工事は、単なる「家具の設置」ではなく 暮らしを支える住まいの基盤 です。
クローゼット・下駄箱・キッチン収納などで生活効率を高める
空間に合わせて設計・施工することで安全性と統一感を確保
デザイン性と機能性を両立し、日常生活を快適にする
収納家具は「物をしまう場所」ではなく、「快適な暮らしを形にする仕組み」といえるでしょう。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
家具には大きく分けて「既製品」と「造作家具」の2種類があります。
既製品は量産されているため手軽に購入できますが、「サイズが合わない」「デザインが空間とマッチしない」といった悩みが付きものです。そこで注目されるのが 造作家具(オーダーメイド家具) です。
造作家具は建物の寸法や住む人のライフスタイルに合わせて設計・製作されるため、フィット感・デザイン性・機能性のすべてにおいて既製品を上回る仕上がりを実現できます。
造作家具の最大の魅力は、空間に「隙間なく収まる」ことです。
既製品ではどうしても数センチの隙間が生まれる → ホコリが溜まりやすい
天井までピッタリ設計できる → 大容量収納を確保
変形した間取りや梁・柱のある空間でも対応可能
「部屋の形に家具を合わせる」のではなく、「家具が部屋そのものに組み込まれる」というイメージです。
造作家具はデザインの選択肢が非常に豊富です。
木材や突板を選んで温もりを演出
メラミン化粧板でモダンな雰囲気に
壁紙や床材と色味を合わせ、空間全体を統一
インテリア全体のコーディネートが可能となり、「家具が浮かずに空間に溶け込む」調和が生まれます。
造作家具は建物に固定するケースが多く、転倒リスクが少ないのが特徴です。特に地震大国・日本では安全面で大きなメリットとなります。さらに、既製品よりも素材や構造にこだわるため、長期間使用できる耐久性を持ちます。
また、部屋の一部として一体化するため、長く使っても「家具が浮いた存在」になりにくく、年月を重ねてもデザイン性を保ちやすい点も特筆すべき強みです。
リビングにぴったり収まるテレビボード
書斎のデスクと一体化した収納棚
子ども部屋の成長に合わせて高さ調整できる本棚
飲食店やオフィスでの什器(じゅうき)
造作家具は住宅だけでなく、店舗やオフィスにも多用され、空間ブランディングの一環として導入されています。
造作家具の特徴は以下の通りです。
隙間を作らない完璧なフィット感
自由度の高いデザインで空間全体を調和
耐久性・安全性に優れ、長く使用可能
「空間に合わせる家具」ではなく「空間そのものを家具で作る」。
それが造作家具の最大の魅力であり、インテリアの可能性を大きく広げる存在です。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
~仕上がりを決定づける家具建具工事~
建物の完成において「内装工事」は最後の大きな工程です。
クロス貼りや床仕上げと同じように、家具建具工事もこの内装工事に含まれ、空間の仕上がりに大きな影響を与えます。
内装工事の流れを大きく整理すると以下のようになります。
下地工事(壁・天井の骨組み、ボード貼り)
仕上げ工事(クロス貼り、床材施工、塗装など)
家具建具工事(収納家具、扉、窓枠の設置)
家具や建具は、クロスや床が完成した後に取り付けられることが多く、いわば内装の仕上げを完成させる最終工程の一部です。
壁紙や床材と家具・建具の色味や素材感がマッチしているかどうかで、空間の印象は大きく変わります。たとえば、ナチュラルウッドの床材に白い収納家具を合わせれば、明るく清潔感ある空間に。逆にダークカラーの建具を合わせれば重厚感が演出できます。
収納家具の容量やドアの開閉方向など、日常生活に直結する部分を整えるのが家具建具工事です。これにより「実際に住んだときの快適さ」が完成します。
家具の造作やドアのデザインは、インテリア全体の雰囲気を決定づけます。シンプルモダン、和モダン、北欧風など、コンセプトに沿った建具選びが重要です。
家具建具工事は、内装の最終仕上げを担うため、少しのズレや不具合が全体の完成度に直結します。
ドアが閉まらない、収納棚が傾いている、といった不具合は施主の満足度を大きく損ないます。
だからこそ、精密な採寸と正確な施工が欠かせません。
家具工事と建具工事は、空間機能とデザインを支える「両輪」
内装工事の最終段階で行われ、仕上がりの質感を大きく左右する
デザイン性・機能性・精度が揃うことで、初めて「快適な空間」が完成する
つまり家具建具工事は、内装工事の中でも住まいの完成度を決定づける重要な工程なのです。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
~空間を支える二つの工事の役割~
建築工事の現場では「家具工事」と「建具工事」という言葉をよく耳にします。
どちらも住宅やオフィス、店舗などの空間づくりに欠かせない要素ですが、その役割や内容には大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴と違いを詳しく解説していきます。
家具工事とは、建物に設置される「造り付け家具」や「据え付け型の収納家具」を製作・設置する工事のことです。代表的なものに以下のような例があります。
キッチンの収納棚やカウンター
洗面所のキャビネット
玄関の下駄箱(シューズボックス)
リビングのテレビボードや壁面収納
オフィスの書類棚やカウンター
いずれも空間の寸法に合わせてオーダーメイドされることが多く、既製品家具では得られないフィット感やデザイン統一感を実現できます。家具工事は、使い勝手や収納力を高め、日常生活の快適性を支える重要な役割を担っています。
建具工事とは、建物内外の「開閉や仕切り」を担う部材を製作・取り付ける工事です。主な建具の種類は以下の通りです。
ドア(開き戸・引き戸・折れ戸など)
窓枠やサッシ
障子や襖(和室の伝統的な建具)
パーティションや間仕切り壁
建具は単なる出入口の役割にとどまらず、プライバシーの確保や空間の分割、さらには断熱性・防音性・防火性を高める機能も持っています。素材も木製・アルミ・スチール・ガラスなど幅広く、デザインや性能面で選択肢が多いのが特徴です。
家具工事 → 「収納や機能性を高める造作物」
建具工事 → 「開閉や仕切りを担う部材」
どちらも住まいや建物の使い勝手を大きく左右し、さらにデザイン性にも直結します。たとえば、収納家具が充実していれば室内がすっきりと片付き、空間の快適性が増します。一方で、ドアや窓のデザイン次第で、空間全体の雰囲気や明るさ、プライバシー性が変わります。
つまり家具工事と建具工事は、役割は異なりながらも「空間機能とデザインを同時に支える存在」なのです。
次回もお楽しみに!
弊社は宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()