-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
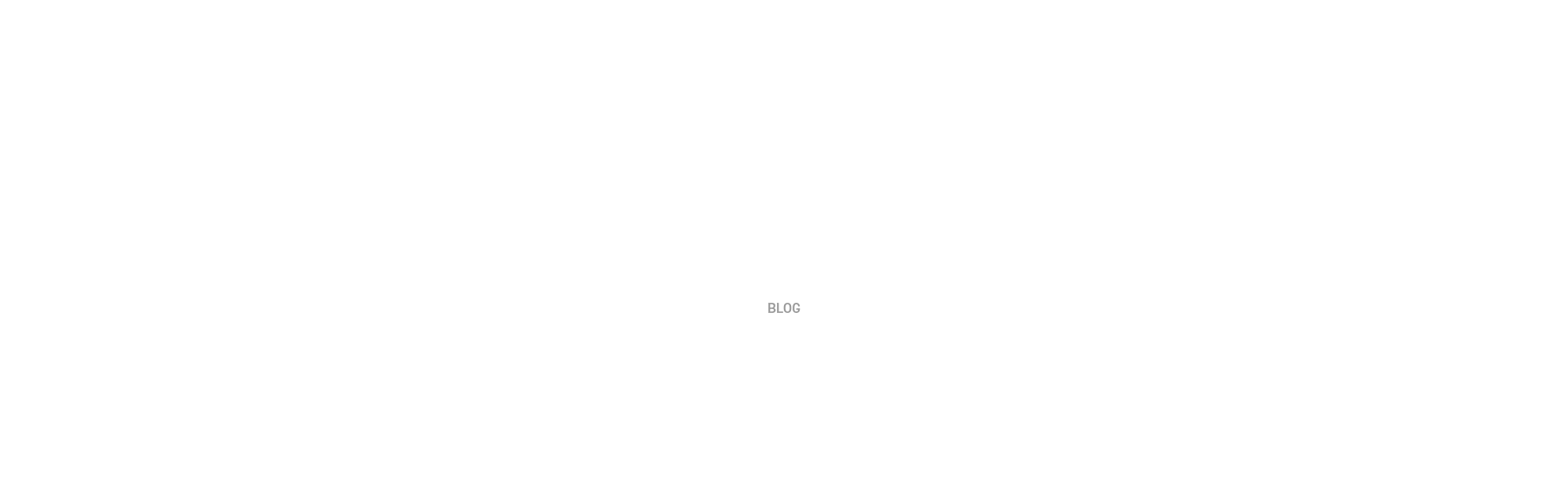
皆さんこんにちは!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っている
塩見木工所株式会社、更新担当の富山です。
ドアや窓、収納家具や間仕切り…。
住まいの快適さやデザイン性を決める重要な要素、それが家具建具工事です。
しかし、その背景には、何百年にもわたる木工技術の進化と職人たちの工夫が詰まっています。
今回は、「家具建具工事の歴史」を、日本の伝統と近代化の流れとともに振り返ってみましょう。
日本の建具文化のルーツは、平安時代にまでさかのぼります。
この頃の住宅は板戸や障子で仕切るスタイル。
和紙を貼った障子は、光を取り込みながら風を通し、日本の風土に合った建具として発達しました。
家具も同様に、収納や食器棚は「箱物家具」として武家や貴族の暮らしに広がります。
江戸時代になると、町屋や武家屋敷の増加とともに、木工職人による建具づくりが盛んになります。
襖、障子、欄間など、繊細な意匠と技術が発展。
この時代には「指物師」と呼ばれる家具職人や、「建具師」と呼ばれる専門職が登場し、日本の木工文化を支えました。
明治期に入り、西洋建築が日本に広がると、ドアや窓にガラスをはめ込む洋風建具が普及します。
さらに、大正デモクラシーの時代には、装飾性を高めた家具や、洋風インテリアが人気となり、和と洋の融合デザインが誕生しました。
戦後の住宅需要の急増により、建具や家具はプレハブ住宅向けに大量生産化されます。
これにより、木製からスチール製・アルミ製へ素材が多様化。
同時に、工場での大量生産+現場での組立という分業が進み、「家具建具工事」は施工技術と設計管理の両方が求められる時代に入りました。
今や建具は単なる扉や窓ではありません。
・断熱性・気密性を高めた高性能建具
・オーダーメイドの収納家具
・引き戸やスライド収納で空間を有効活用
さらに、バリアフリー建具や防音ドアなど、暮らしの質を高める技術も次々と登場。
素材も天然木だけでなく、樹脂やアルミ、複合材が一般化し、メンテナンス性や耐久性も大幅に向上しました。
家具建具工事は、住まいの文化とともに進化してきた技術です。
昔ながらの木工技術をベースにしながら、時代ごとのニーズに応え続けてきた職人の知恵と工夫が、今の快適な暮らしを支えています。
次回は、そんな家具建具工事を成功させるための**「鉄則」**を、現場目線で解説します!
次回もお楽しみに!
宮崎県日向市を拠点に木製家具や建具の製作を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()